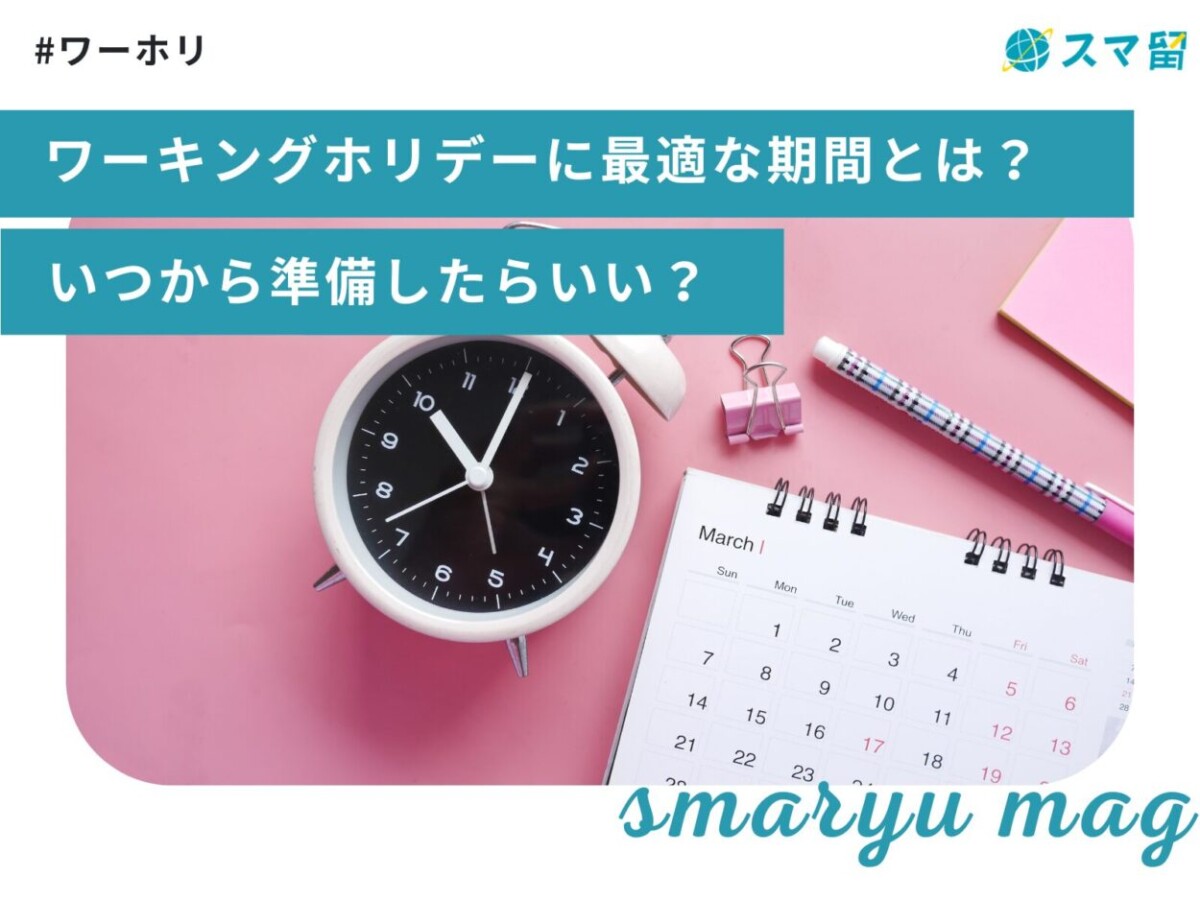
働きながら語学を学んだり観光したりできるとあって、ワーキングホリデーは根強い人気を誇っています。
しかし、滞在期間や時期、国や地域などを自分で選ぶシステムだけに、どれくらいの期間行くべきかなど、ワーキングホリデーの期間にまつわる疑問は多いもの。
ここでは、みんなが気になるワーキングホリデーの期間について解説します。
CONTENTS
ワーキングホリデーの期間について考える前に、そもそもワーキングホリデーとはどのような制度なのか、基本情報をおさらいしておきましょう。
ワーキングホリデーとは、日本との協定を結んでいる国と地域を対象に、1年間滞在することができるビザのことです。
1つの国に対し、ワーキングホリデーのビザが使用できるのは1回で、滞在期間中は現地で働くことができます。
ワーキングホリデーは休暇を過ごすことを主目的としており、滞在中に必ずしなければならないことはありません。働くのも観光するのも、勉強するのも基本的に自由です。
ビザを申請できるのは、原則として18~30歳まで。若いときしか利用できないため、学生はもちろんですが、社会人が利用するケースも多いです。なお、滞在期間は、国や地域によって多少異なります。
ワーキングホリデーは世界中どこの国でも行けるわけではなく、日本と協定を結んでいる特定の国と地域に限られています。
2025年7月現在、日本からのワーキングホリデーを受け入れているのは29の国と地域です。協定国は毎年のように増え、現在交渉している国もあります。行きたい国が現在はワーキングホリデーの協定国ではない場合も、いずれ協定が結ばれる可能性はあるでしょう。
ワーキングホリデーの期間や条件などは、国や地域によって多少異なります。
また、年間のワーキングホリデーのビザ発給枠も、国や地域によって上限があり、上限数を公開していない場合もあります。
海外留学とワーキングホリデーの決定的な違いは「現地で働けるかどうか」という点でしょう。留学するときは、短期ならビザが必要ないこともありますし、長期なら学生ビザを取得するのが一般的です。
しかし、ビザがなかったり、学生ビザで入国したりする場合、原則として、現地で働いて収入を得ることはできないとされています。
そのため、留学するときは滞在費用をあらかじめ用意して渡航することになりますが、ワーキングホリデーのビザなら、現地で働き、その収入を滞在費にあてることが可能です。
ワーキングホリデーは休暇を楽しむ目的で利用する、自由度の高い制度です。ただし、ワーキングホリデーのビザには申請の条件があり、いつでも誰にでも発給されるわけではありません。
また、ワーキングホリデーを利用するなら、ビザの申請以外にもすべきことがあります。詳しくご紹介しましょう。
外務省のウェブサイトによると、ワーキングホリデービザの発給要件は以下のようになっています。
<ワーキングホリデーのビザ発給条件>
・一定期間、相手国・地域において、主として休暇を過ごす意図を有すること。
・ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
・子または被扶養者を同伴しないこと。
・有効な旅券と帰りの切符(または切符を購入する資金)を有すること。
・滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
・以前に、ワーキングホリデービザを発給されたことがないこと。
まとめると、「ワーキングホリデー協定国または地域に、一定期間住むための初期費用と往復交通費が確保できている18~30歳の人」ということになります。上限年齢については国や地域によって多少異なります。
ちなみに、年齢はビザ申請時で、ビザは発行から1年間有効ですので、30歳のうちに申請していれば渡航時に31歳でも問題ありません。
滞在する国によって、教育機関に就学できる期間や、就労できる期間に上限が設けられているなど、個別の条件がある場合もあります。
ワーキングホリデーに限らず、外国に3ヵ月以上滞在する場合は、現地の日本大使館か総領事館に「在留届」を提出することが法律で義務付けられています。
在留届を提出することにより、緊急事態の際、日本大使館や総領事館が、安否確認や緊急連絡がしやすくなります。
海外ではいつどんな形で事故や事件、災害に巻き込まれるかわかりません。一刻も早く身の安全を確保し、日本にいる家族に安否を伝えるためにも、現地入りしたら在留届を提出することをお忘れなく。
ワーキングホリデーは基本的に1年間有効のビザですが、滞在期間については1年以内で自由に決めることができます。上限ギリギリまでステイするのも、短期集中で海外生活を体験するのも、自分次第です。
しかし、せっかくワーキングホリデーを利用するなら、半年以上の滞在をおすすめします。その理由をご紹介します。
ワーキングホリデーは極端にいえば、最短1日でも利用可能です。しかし、3ヵ月以内の短期の滞在なら、ビザなしで入国できる国もたくさんあります。
わざわざ面倒な申請をしてビザを発給してもらったからには、長期滞在して、ワーキングホリデーでしかできない体験をたくさん味わってみてください。
特に、海外で働ける就労ビザは発給されにくく、海外で働く経験はなかなかできるものではありません。ワーキングホリデーを利用して海外で働けば、今後の人生に活かせるすばらしい経験になるはずです。
ワーキングホリデービザは、原則として1つの国につき、1回しか発給されません。一度ワーキングホリデーを利用してしまえば、その後その国に旅行で訪れることはできますが、半年以上の長期滞在は難しくなります。
長期滞在できるビザとして学生ビザがありますが、学校に通って学ぶという条件がありますし、就労はできないことがほとんどです。
ワーキングホリデーという限られた機会ですから、半年から1年と、できるだけ長期滞在してみてはいかがでしょうか。
ワーキングホリデーでは、仕事は自力で見つける必要があります。求人を探して応募して、面接を受けて、採用されたら研修を受けてと、段階を踏んでいくだけで時間がかかるでしょう。
滞在期間が短い人ほど、働ける時間も短くなってしまいます。さらに、すぐに仕事が見つかるとも限りません。
雇う側としては、できるだけ長く働いてくれる人を優先的に採用することが多いので、短期滞在だとどうしても仕事探しのハードルが上がってしまうこともあります。
現地で働くことを目的としているなら、半年以上の滞在がいいでしょう。
ワーキングホリデーの目的に、語学の習得を挙げる人は多くいます。当初は語学学校に通う人が多く、短期滞在の場合は、通学だけで期間が終わってしまうかもしれません。
また、短期滞在だと、ようやく現地の言葉に耳が慣れ、少し会話ができるようになったかな…というところで帰国日を迎えてしまうことも。外国語でのコミュニケーションが楽しくなってきたところで終わってしまうのは、もったいないこと。
語学力をアップしたいなら、半年以上の期間を確保しておきたいところです。
ワーキングホリデーは、協定国に1年間滞在できるビザと説明しましたが、中には1年以上に延長できる国もあります。滞在期間が長くなれば、さらにできることは増えるはず。
では、1年以上滞在するには、どうすればいいのでしょうか。滞在期間を延長できる国と、延長する方法について紹介します。
ワーキングホリデー協定国の中で、オーストラリアは条件を満たすことで、最長3年まで期間を延長することができます。
実際のところ、延長というよりは、ワーキングホリデービザをトータルで3回申請できるといったほうが正しいでしょう。
2回目のワーキングホリデービザを「セカンドワーキングホリデー」、3回目を「サードワーキングホリデー」と呼んでいます。
セカンドワーキングホリデー、サードワーキングホリデーを利用するためには、オーストラリア政府が定めた特定の地域、または職場で3ヵ月働き、それを証明できることが条件です。
1年目の滞在期間が終わって帰国してから、セカンドワーキングホリデー、サードワーキングホリデーの申請を行うことも可能ですが、申請の年齢制限は延長されないため、注意が必要です。
つまり、1回目の滞在が終わった時点で31歳になっていれば、セカンドワーキングホリデー、サードワーキングホリデーを利用することはできません。
オーストラリアのお隣、ニュージーランドでも条件を満たせば滞在期間を3ヵ月間延長することができます。延長するには、国内のファーム(農場)で3ヵ月以上の労働を行っており、それを証明できることが条件です。クリアすれば、最大で1年3ヵ月滞在することができます。
延長の申請は、ニュージーランドの移民局に出向くか書類を郵送する必要があり、申請料を支払うことになります。
オーストラリアやニュージーランドは、指定された労働を条件として滞在期間を延ばすことができますが、イギリスはそもそもワーキングホリデーで2年間まで滞在が可能です。イギリスのワーキングホリデービザを取得できれば、自動的に最長2年間、イギリスに滞在できることになります。
また、難関とされてきたイギリスのワーキングホリデービザですが、2024年1月より年間1,000人だったイギリスの年間のワーキングホリデービザ発給枠が6,000人へと拡大し、抽選制から先着順へと変更されました。確実に以前より申請しやすくなったため、イギリスでのワーキングホリデーを検討していた人にとってはまたとないチャンスでしょう。
ワーキングホリデーを利用する場合、渡航する国を選んだりビザを申請したり、さまざまな準備が必要です。万全の状態でワーキングホリデーを迎えるためには、いつから準備を始めても早すぎることはなく、短くても半年、できれば1年は準備期間があるのが望ましいです。
具体的なワーキングホリデーの準備スケジュールをご紹介します。
<1年~半年前>
・ワーキングホリデーの情報を収集する
・ワーキングホリデーの費用を貯める
・ワーキングホリデーの目的を決める
<半年~3ヵ月前>
・渡航先の国を決める
・ワーキングホリデービザを申請する
・(なければ)パスポートを申請する
・語学学校や滞在先を手配する
<3~1ヵ月前>
・航空券を手配する
・海外留学保険に加入する
<2週間前~出発>
・役所で手続きを行う
ワーキングホリデーの準備は、さまざまな手続きや申請が必要で、何かと悩むことが多くなります。
スマ留では、ワーキングホリデーについて、無料でカウンセリングを行っています。公式LINEでサポートすることもできるため、お気軽にご相談ください。
長期間、外国で暮らすことになるワーキングホリデー。現地で生活するためにはさまざまな費用がかかり、多少働いて収入が得られるといっても、しっかり準備しておきたいもの。
具体的にはどんな費用がかかるのか、内容をご紹介します。
ワーキングホリデービザを取得しないことには、渡航できません。ビザの発給は無料の国も多いですが、申請費がかかることもあります。例えばオーストラリアでは、670オーストラリアドル(約63,191円)が必要です(2025年7月現在)。
国によって金額はもちろん、申請方法も異なり、申請から発給までは時間がかかることもあります。余裕を持って、事前に確認しておきましょう。
また、ワーキングホリデーのビザ申請は、「滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を持っていること」が条件になっています。
例えばイギリスは、2,530ポンド保有していることを証明しなければならないなど(2025年7月現在)、具体的に金額が決まっている国もあります。申請費とは別に、こういった費用も事前に用意しておく必要があります。
ビザと並んで必要になるのが、渡航費です。ほとんどの国へは、飛行機を使って移動することになります。韓国のように近くの国であれば手頃な金額で済む一方、ヨーロッパや南米など、現地入りするために高額の航空チケット代がかかる場合もあるでしょう。
ワーキングホリデーで入国するにあたっては、往復の航空チケットがあるか、帰りのチケットを購入できる資金があることが条件です。行きだけでなく、帰りの航空チケットについても考えておきましょう。
保険料も、渡航前に必要な費用のひとつです。専用の「ワーキングホリデー保険」を用意している保険会社も多くあります。
言葉も文化も社会システムも違う異国では、いつどんな形で事故や事件、災害に遭うかわかりません。慣れない環境で体調を崩すこともあるでしょう。ビザ申請の条件に保険の加入を義務付けている国もあります。
安心してワーキングホリデーを利用するためにも、海外留学保険の加入をおすすめします。
滞在する国の物価や希望の暮らしによって変わりますが、生活費として、食費や住居費、交通費、通信費といった費用がかかります。現地で友達ができれば、交際費も必要になるでしょう。
ワーキングホリデーは就労が可能なため、現地で生活費を稼ぐこともできます。しかし、すぐに仕事が見つかるとは限りませんし、生活費のために働いてばかりでは、せっかくのワーキングホリデーの期間を有意義に過ごせません。
渡航前に、あらかじめまとまった費用を用意しておいたほうが良いでしょう。
ワーキングホリデー中、最初の数ヵ月間は、語学力のアップのために語学学校に通う人が多いです。その場合は、学費も予算に入れておく必要があるでしょう。学校によって受けられるカリキュラムやサービス、利用できる施設などが異なり、学費も大きく差が出ます。入学金や教材費なども含めていくらかかるのか、自分がいくらまで出せるのか、しっかり考えておきましょう。
ワーキングホリデーは、基本的には1年間協定国に滞在できる制度ですが、国や地域によって、期間は多少違ってきます。期間によってできることは変わりますし、自分にとって最適な期間を決めるのは簡単ではありません。限られた年齢でしか利用できないワーキングホリデーだから、悔いのないようにしたいですよね。
留学サイトの無料留学カウンセリングや説明会などを積極的に利用して、自分に合ったワーキングホリデーのプランを考えましょう。
スマ留では、無料のカウンセリングを毎日開催しています。より気軽に、公式LINEからご相談いただくことも可能です。
ワーキングホリデーを有意義にするため、どんなことでもご相談ください。
Q&AまとめQ&A