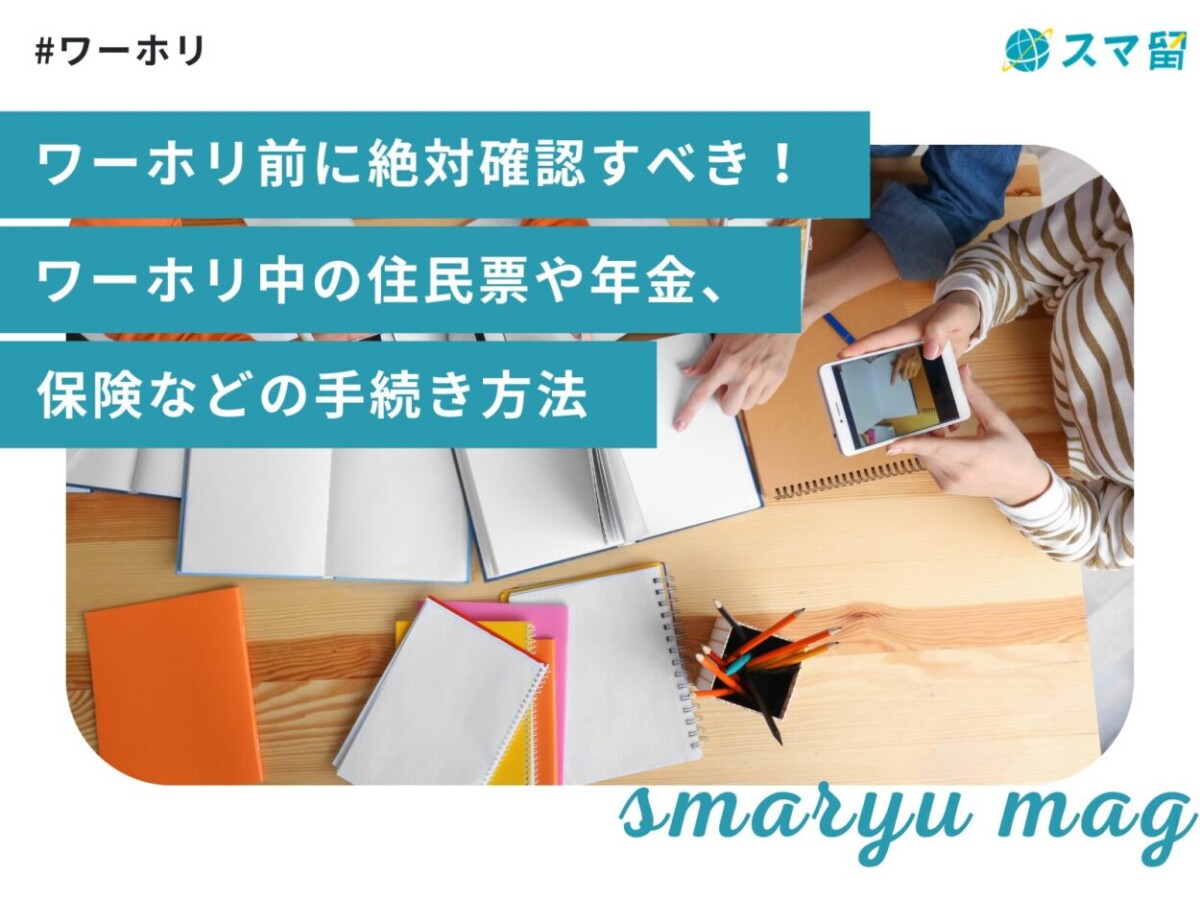
ワーホリの準備は「 出発の1年前」から始めるのが安心!
ビザ申請や渡航準備だけでなく、 住民票・年金・保険など役所手続きも忘れずに行うことが、金銭面・手続き面でのトラブルを防ぐカギになります。
特に 海外転出届の提出で、住民税・国民年金・健康保険の支払い義務を回避できる一方、住民票の喪失による制約もあるため、メリット・デメリットを踏まえて計画的に対応しましょう。
ワーホリで失敗したくない あなたへ
スマ留なら、語学学校の空き時間や空き場所を活用することで、従来の留学費用の最大半額*を実現!さらに、ビザ取得や現地での生活サポートも充実しています。
※2024年及び2025年に実施した業歴10年以上の複数の競合他社を対象とする調査結果に基づく
CONTENTS
ワーキングホリデーの手続きは、国によって多少の違いはありますが、計画的に進めるために、出発の約1年前から準備を始めると安心です。
・行きたい国を決める
・予算を計算する
・ワーホリビザの条件を確認
・パスポートの有効期限確認(残存期間が1年以上あるか)
・必要書類を準備(銀行残高証明、英文履歴書、健康診断書など)
・語学力向上
・ビザ申請手続きの開始
・必要な予防接種の確認と実施
・航空券の手配
・海外保険の加入
・住まいの手配
・銀行口座&携帯電話の準備
・国際免許証の取得(車を運転する予定がある場合)
・ビザの承認確認(渡航前に必ず取得状況をチェック)
・出発の手続き(住民票の手続き、税金・年金の確認)

まずは、海外転出届からみていきましょう。
ワーホリ中の、住民票や保険料はどのようになるのでしょう。 日本では、海外転出届の有無によって、住民票や保険料などが変わります。この章では、海外転出届についてご紹介していきます。
海外転出届とは、 1年以上日本を離れる際に提出するものです。海外転出届を提出することによって、日本にいない状態(住民票を「抜いた」状態)になります。そうすることで日本にいたらかかるはずだった税金や年金などの負担を軽くすることができます。提出する場合は、渡航する14日前から手続きが可能です。海外転出届を提出する際は、パスポートと印鑑をもって、転居届を提出する役所に提出します。
※自治体によって対応方法が異なる場合もございますので、必ずご自身の自治体をご確認ください。
海外転出届は、1年以上海外にいく際に、基本的に提出しなければならない書類です。1年未満の方は、提出する義務はありませんが、提出することもできます。海外転出届を提出するメリット・デメリットは、どのようなことがあるのでしょう。
海外転出届を提出するメリットは、住民税や保険料など、一部支払い義務がなくなることです。詳しく見ていきましょう。
住民税の支払い義務がなくなる
海外転出届を出すと、日本に住んでいないことになるため、住民税の支払い義務がなくなります。
特にこれまでお仕事をされていた方には、金銭的に最も大きなメリットです。
(※ただし、1月1日時点で住民票が残っている場合は、支払い義務があるので注意が必要です。)
国民健康保険の支払い義務がなくなる
住民票を抜くことで、国民健康保険の加入者ではなくなり、保険料の支払い義務もなくなります。
ただし、親御様の扶養に入っている学生の方や、パートナーの勤め先の健康保険に加入している方などはこのメリットはあてはまりません。
国民年金を支払わなくてよくなる
日本に住民票がない人は、国民年金への加入義務はありません。
そのため、海外転出届を提出した後は海外にいる間の年金の支払いをする必要がありません。
17,510円/月(令和7年度時点)の節約になり、年間で210,120円の支払い免除になります。
海外転出届を提出することで多くの金銭的メリットがありますが、当然デメリットもあります。
届出を行う際は、デメリットもかんがみて、慎重に判断しましょう。
住民票を発行できなくなる
海外転出届を行う=住民票を抜くことになるため、当然住民票を発行することができません。
海外に滞在中は住民票が必要になることはありませんが、 特に渡航前に注意しましょう。
住民票が必要になることが想定される場合は、届出は渡航直前にしましょう。
銀行口座開設やクレジットカード新規発行ができなくなる
銀行口座の開設やクレジットカードの新規発行には、本人確認書類が必須です。
住民票を抜くと、健康保険証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が失効し手続きが行えなくなるため注意しましょう。
ただし、既に発行しているカードや銀行口座は使えます。 海外用に口座を開設する場合やクレジットカードを発行したい場合は前もって準備しましょう。
失業手当を受けられなくなる
ワーキングホリデーに行く方の中には会社を退職して渡航する方もいるかもしれません。日本の雇用保険では、一定の求職活動をすることで自己都合であっても失業手当が給付されますが、海外転出届を提出した方はこれをもらえません。海外へ行けばそもそも求職活動ができないので、これは諦めなければいけませんね。
健康保険未加入状態になる
住民票を抜くと、日本の健康保険に加入していない状態になります。
つまり日本に一時帰国などをしたとき、保険を適用して医療サービスを受けることができなくなり、病院では10割負担になります。
また、日本の健康保険加入者は海外で受けた医療サービスについても、手続きを行うことで保険が適用されます。海外留学保険や旅行保険のような全額控除ではありませんが、国民健康保険加入者に補償があることも覚えておきましょう。
さて、次の章では国民年金と健康保険について、海外転出届を出す場合と出さない場合を詳しく見ていきましょう。
海外転出届を提出すると、ワーホリ中、住民票を抜いておくことができます。住民票を抜くことによって、国民年金を支払う必要がなくなります。この章では、ワーホリ中の国民年金についてご紹介していきます。
海外転出届を提出することによって、年金を払わなくてもよくなります。しかし、払わないことで将来にもらえる年金の金額が変わってしまうため、注意が必要です。
提出しない場合は、ワーホリ中も年金を支払う必要がありますが、将来、年金をすべて受け取ることができます。ワーホリ中に年金を支払う方法は、保険料納付猶予制度を利用する方法、後納制度を利用する方法があります。
保険料納付猶予制度
所得が少ない方を対象に年金の免除を申請できる制度です。
海外大学への留学やワーホリに行く場合、日本での収入がなくなり、年金の支払いが困難になる場合に該当します。
全額、4分の3、半額、4分の1、の4種類の控除項目があります。
後納制度
海外の滞在が2年以内の場合、帰国後に払うことができる制度です。
この制度を利用することによって、ワーホリ中の年金を帰国後に支払うことができます。

海外転出届を提出することによって、ワーホリ中、住民票がなくなるため、国民健康保険から抜けることになります。この章では、ワーホリ中の国民健康保険についてご紹介していきます。
海外転出届を提出することで国民健康保険から外れるため、海外健康保険に加入する必要があります。海外では、治療費が高いため、海外健康保険に加入していないと高額な治療費を請求されます。海外健康保険の選び方は、5章でご紹介していきます。
海外転出届を提出しない場合は、国民健康保険の保険料を支払う必要があります。日本の保険に入っているため、海外健康保険に必ず入らないといけないということはありません。日本の保険料を支払っている場合は、海外でかかった治療費が日本で換算されてお金が戻ってくることがあります。しかし、海外の滞在期間が1年以上という条件があります。
ワーホリで、住民票や保険など以外に役所で手続きする必要があるものは、何があるのでしょう。この章では、住民税や保険料など以外に手続きすることについてご紹介していきます。
住民税は、前年度に稼いだ分の税金を払う必要があります。住民税が決まるのは、1月1日です。1月1日に住民票がある場合は、前年度に稼いだ分の税金を支払う必要があります。しかし、1月1日までに住民票がない場合は、住民税を支払わなくてもよくなります。
海外転出届を提出した際には、マイナンバーカードの返却が必要です。しかし、渡航後に失効されて、家に送られてきます。失効されたマイナンバーは、帰国後に使うことがあるため、保管しておきましょう。
ワーホリ中の確定申告は、事前に申告することができます。確定申告は、2月~3月に申告するため、事前に申告する際は、事情を説明しましょう。事前に申告する場合は、源泉徴収票、印鑑、所得税控除に必要な明細書、納税をしている口座情報が必要です。

ワーホリ中は、住民票を抜いて保険や年金を払わなくてもよくなりますが、海外健康保険に加入が必要です。海外健康保険は、保険会社やプランが多いため、どの保険を選べばよいのでしょう。海外健康保険は、ワーホリで渡航する国やプランで決めるなどの選ぶ方法があります。
ワーホリする国によっては、医療の技術が異なるため、治療費にも差があります。また、 海外では、救急車を呼ぶだけでもお金がかかり、日本より治療費が高くなってしまうことがあります。そのため、ワーホリ保険に加入しましょう。
補償プランは、保険会社によって異なります。ワーホリする国によって、必要な補償プランが組まれていないと意味がありません。そのため、必要な補償プランが組まれている保険会社を選びましょう。また、保険会社によって費用が異なります。費用を抑えたい人は、補償プランを組み替えられる保険会社を選ぶとよいでしょう。補償内容や費用など、難しいと感じている方は直接留学エージェントに相談することを強くおすすめします。
ワーホリ中の住民票や年金などは、海外転出届を提出することによって異なります。海外転出届を提出した場合は、住民票がなくなり、年金や国民健康保険を支払う必要がありません。提出しない場合は、年金や国民健康保険などの税金をワーホリ中に支払うことになります。海外転出届を提出する場合は、役所に渡航する14日前までに提出しましょう。
また、海外転出届を提出した場合は、国民健康保険から抜けてしまうため、ワーホリ保険に加入しましょう。ワーホリ保険に加入していないと高額な治療費を請求されることがあります。ワーホリ保険に加入する保険会社を選ぶ際は、補償プランや費用を比べてみるとよいでしょう。
ワーキングホリデーを今まさにご検討中の方は、まずはカウンセラーへ無料相談することを強くおすすめします。費用や国、就労先と考えることの多いワーキングホリデーも、留学のプロであるカウンセラーがあなたを丁寧にサポートします。
「留学費用が気になる」という方は、料金シミュレーションしてみるのもおすすめです!
Q&AまとめQ&A